この記事では、文書による命令等のプロセスについて、次の内容を説明します。
第1回
- 文書主義と組織運営
- 原則として文書による命令・報告に基づき、組織運営が行われる。
- 証拠性・同時性・客観性・保存性の利点のため。
- 組織を動かすには、組織的な検討を経て、適切な権限に基づく命令が必要
- 原則として文書による命令・報告に基づき、組織運営が行われる。
- 「上位者の仕事をする」ということ
- 指揮官が部下の提案を承認することで、命令が生まれる。
- 指揮官の命令を実際に作り発するのは部下
- 指揮官自身が能動的に命令を発すると
- 指揮官のキャパシティによる制約大
- 部下が育たず、指揮官が指揮不能になると組織が瓦解
- 指揮官が承認したことを明確にするために、文書が必要
- 指揮官が部下の提案を承認することで、命令が生まれる。
第2回
- 「文書」を巡る複雑な問題
- 海自での「文書」は状況により指すものが異なる。
- 「正式な文書」としての文書
- 「一般命令」や「通達類」など
- 経費の支出根拠になる。
- 艦長など官職印のある者(通常は1佐以上)だけが発簡できる。
- 発簡年月日と発簡番号が明記される。
- 「書面による情報伝達」としての文書
- いわゆる「報告資料」「実施要領」など
- 一定の体裁をもって、書面にまとめられている。
- 「正式な文書」のような効力は持たないが、情報伝達に用いられる。
- 「行政文書」としての文書
- 公文書管理法上の公文書
- 状況により、電子メール、写真、メモ書きなども含まれる。
- 保存や開示について法令を遵守する必要
- 「正式な文書」としての文書
- 文書について考える場合、どの「文書」を指すのかを明確に認識する必要
- 海自での「文書」は状況により指すものが異なる。

第3回
- 「行政文書管理の手引」を読み込もう。
- 「文書」の作り方
- 合議制
- 会議で意思決定する代わりに、関係者が順次案文に修正を加えることで調整
- Wordの設定
- 一般命令・通達類
- 起案用紙を用いるのが特徴
- 訓練実施要領
- 合議制
 水雷長 遠見1尉
水雷長 遠見1尉やあ、未来。入校してしばらく経ったけど、なんか困ってることある?



ええ。色々と。
「共用ロッカーの格納状況が悪いので、統制を取れ」って、幹事付から言われたんです。で、どう収めるかはだいたいまとまったんですけど、紙に書いて配ったら、幹事付からメチャクチャ怒られたんですよ。酷い話じゃありません?



あー、よくあるやつだね。
アレでしょ?「どうやったら改善できるか、文書作って持って来い」って言われてるんでしょ?



ええ、そのとおりです。
なので紙に書いて持っていったら、「こんなの文書じゃない」だのなんだのと、また怒られて。
全く。なんでこんなことをしなきゃいけないんだか……。



まぁ、ロッカーの入れ方なんて些末なことで何故そんな面倒な、って思うよね。
ただ、この仕事をしていると文書とのお付き合いは避けられないから、早いうちに勉強しておいた方がいいよ。



はぁ。
文書主義と組織運営
文書の利点



組織を運営するにあたっては、文書で命令や報告を行うのが原則なんだ。これはなんでだと思う?
証拠性



言った、言わないの話で揉めないためじゃないですかね?



そうだね。口頭で伝えると内容に欠落が生じることがあるけど、文書なら文字になっているからこそ100%相手に伝えることができる。(伝わるとは言ってない



あれ?でも、届けてる途中で1ページ紛失しました、みたいなこともあるんじゃないですか?



ある。だから、文書を受け取る側は、受け取ったときに枚数を確認して欠落が無いか確認するんだ。問題があったら送った側に確認や再送を要求する。問題が無ければ受け取った文書の一覧に登録する。この一連の手続きを「接受」と言うんだけど、これによって伝達に問題が無かったことが保証されるんだ。



なるほど、TCPみたいなもんですね。



で、文字になっているからこそ、後になってトラブルが起きたときは、文書の内容に問題が無かったか、追跡調査できる。
同時性



もう一つの利点は、多数の相手に対して同時に情報伝達できる点だね。無線電話や電子メール、メッセンジャーでも同じことは言えるけど。少なくとも、口頭でひとりひとりに伝えていくよりは同時性が高い。



特に、偉い人……海上幕僚長とか、防衛大臣とか、そのレベルになると命令を発するだけで、伝えないといけない相手が数十件、数百件に及んでしまう。



その1件1件に電話掛けて説明するより、文書を複写して一気に郵送した方が手っ取り早いってことですね。



うん。それに、真に同時性を期したい場合は、封書を渡して、ある時刻に一斉に開封させるという手もある。ボクはそういうケースを見たことないけど……。
「真に同時性を期したい場合」とは何か……と言えば、秘密保全上の理由がある場合です。「同時性がある」とは言え、伝送や接受にかかる時間にはどうしても相手方による差が生じるので、先に接受を済ませた部隊から情報が漏えいする恐れがあります。そこで開封時期を指定した封書を渡すことで、必要な時期までは漏えいさせないようにするのです。
客観性



もう一つ、文書に関する参考資料に挙げられているのがコレ。



客観性って……どういうことです?



「話し方や態度による先入観を与えることがない」……とされている。
つまり、口頭だと「●●をやれ!とにかくやれ!もたもたするな!」と言われるか、「(ぁ……だりぃ……)あー、●●な、とりあえずやっといてくれ。うん。いいね?」と言われるかで、受け手の印象は大きく変わってしまう。でも文書だと「●●を実施せよ」で統一されるから、主観に左右されない。



まあ、それはだいたい分かるんですが。実際どうなんです?



まあ……、命令には大抵、幕僚や隊付からの説明が加わるからね。「本件、司令官が最近気にされているので注意してください」とか「ぶっちゃけ、そんなに重要じゃないので実績さえ作ってくれたらOKです」とか。だから、必ず主観が混じる。



とは言え、「口頭でそう言われたから」って文書を公然と無視したらダメだよ。
文書だけだと、あまりにも画一的になりすぎてしまうから、ちょっとだけ重み付けをしてるんだ。それがちょっとで済まなくなってしまうことがあるだけ。
保存性



最後にコレ。



さっきの「証拠性」と同じですかね?保存できるから後で検証できるって。



そうだね。それに加えて、「反復して使用できる」というのもポイントなんだ。
お役所の前例主義に通じてしまうところではあるんだけど、前例があれば、どういうやり方で臨んだか、その結果どうなったかがある程度分かるんだ。上手くいってたなら、とりあえず前回とほとんど同じ実施要領で臨んでも大丈夫だろうってことになる。つまり、前回の命令文をコピペして、人やモノの配置を微調整するだけでOK。



確かに、後に残らない媒体で命令が出ると、改めて一から作り直さないといけないんですね。
広告
組織的検討と適切な権限による命令



それからもう一つ、重要なポイントがある。組織が動くときには、原則として、組織的な検討を経た上で、適切な権限によって命令が行われないといけないんだ。



どういうことです?



まず、組織的検討。これは誰か個人の思いつきで組織が動いてはいけないってこと。軽微な内容とか、緊急時の対応だと、個人のスタンドプレーになることもあるんだけど、それはあくまで例外。



ふーん。でも、それだと意思決定が遅くなりませんか?



うん。それはまさしく組織の抱える問題だね。ただ、だからといって根回ししないで物事を決めると、他のセクションがやっている取り組みと競合して足を引っ張ったり、「いざ始めてみたら、全然準備出来てませんでした」なんてことになってしまったりする。
組織的な検討自体は避けられなくて、それをいかに素早くやるか、というのが今の組織の課題になってるんだ。



確かに、会社で「ワンマン社長が~」って話が出ると、だいたい経営がめちゃくちゃになってるって話ですもんね。



うん。トップダウンで事細かに物を決めるのは、下に決める能力がない場合は効果的なんだけど、長続きはしない印象だね。



それから、適切な権限の下に命令すること。
「ひとなみ」という部隊を動かしたいなら「ひとなみ」艦長の命令が必要だし、第1学生隊という組織を動かしたいなら第1学生隊長の命令が必要。……分かる?



そりゃ分かりますけど。



いや、多分まだ分かってないと思うよ。それが分かってるなら、未来は自分のやったことが結構マズいことに気付くはずなんだ。



そうですか?何かマズいことしてます?



今回、未来は共用ロッカーの整頓状況を改善するために、学生内で統制事項を作るよう、幹事付から指示されたんだよね?



ええ。



つまり、学生隊という組織について、一定のアクションを起こすように指示されたってワケ。なのに、未来は自分の独断で紙を作って学生に配ってしまった。本来なら、学生隊長の命令が無いといけないのに。つまり越権行為だよ。



そんな大げさな。「こういう風に格納してください」って、お願いして回っただけですよ。



でも、その結果として学生たちはその「お願い」に拘束されて、一定のアクションをすることになる。



確かに「たかがロッカーの格納要領ごときで、そんな大げさな」っていうのはマトモな感性だよ。でも、あと1、2年もすると、格納するのが掃除機や角ハンガーから、弾薬や秘密文書、現金に変わるんだ。だから、今は手を抜かないで欲しい。掃除機や角ハンガーのうちは、いくら失敗してもやり直しがきくから。



はい……。



それにしても、4月のうちからそういう指示が出ること自体、幹事付からはかなり良い評価をされている証だから、そこは誇りに思った方が良いよ。自分のことでいっぱいいっぱいな奴には、幹事付もそういう指示しないから。



それはそれとして、扱うモノがどうであれ、組織を動かすには適切な権限の下に発せられた命令が重要、というのはよく分かって欲しい。仮に「何もしない」というアクションをするにしても、「労働力」というリソースは刻々と消費されていくんだ。



本来なら、教育や訓練、隊員の休息に使えたはずの時間が、「統制事項に従う」というアクションに使われてしまう。その原資はどこにあるかと言えば、国民の税金、公金なんだ。
軍事組織だろうが、公金の適切な使用を求められるのは普通のお役所と一緒。だから、部隊が適切に活動しているかは必ず会計監査で見られているよ。



そこで、「適切なプロセスに従って部隊が動いてました」って説明できないといけないんですね。



そういうこと!
自衛官と言えば、24時間365日定額働かせホーダイプラン。何が労働時間の管理じゃ!……というご意見も、まぁ分かります。とは言え、ご理解戴きたいのは、公金は「100%適切であることが証明されない限り、支払いされないモノ」だということです。
海幕や会計検査院は定期・不定期に監査を実施しており、仮に支払い済であったとしても、手当や旅費の返納、付与した休暇の取り消しを命ずることがよくあります。そのきっかけはたいていの場合、航泊日誌や行動の根拠となる命令の不備。たとえ実際にはその仕事をやっていたのだとしても、そのプロセスが適正であったことを請求者が証明できない限り、公金を支出することが出来ないのです。



ましてや「お願い」というのが、良くない。「お願い」だけで組織が動いてしまったら、結局誰の責任でやったのか、とても曖昧になってしまう。
実際には、そういう根回しも重要ではあるんだけど、その終着点として、必ず命令を出さないといけないなんだ。



ボクが以前働いていた艦では、長期任務行動の後、帰る途中で広報寄港するよう、司令から口頭でお願いされていたことがあったんだ。
みんな内心早く帰りたいのに嫌だなと思いつつ、司令が言うから仕方ないって準備してたんだけど、任務行動が終わって帰り始めても全く命令が出ない。隊付に確認を入れても応答がない。



あら、そんなことが。



そんな状況に業を煮やして、艦長はとうとう「命令が出ていない以上、寄港する正当性が無い」と宣言して、母港へ針路を変えるように指示したんだ。「電話1本で部隊を動かそうなんて、舐めるんじゃねぇ!」ってキレてた。うん。
そしてら、隊付が大慌てで「命令は出ますから!」って電話してきて、その日のうちに「広報を実施せよ」って命令文が出たから、艦長は仕方なく従ったよ。ちなみに、命令文の中身は寄港地の名前以外、日付も目的も実施内容も、全部「別に示す」とかいうクソ文書だったけど……。



なんかよく分かんないですけど、命令がそれだけ重いってことですね?



そういうこと。
今回の場合、学生隊に対してロッカーの格納要領を統制する命令を出したい。そしたら、学生隊長の命令文書が必要になるということなんだ。
広告
「上位者の仕事をする」ということ



いや、ちょっと待ってくださいよ。そしたら、幹事付が私に言うの、おかしくないですか?
学生隊長の命令が必要って言うなら、そんなの学生隊長に言えばいいじゃないですか。



ふふ、そうだよね?ボクも入隊前はそう思ってた。
「部下の提案を承認する」ことで生まれる命令



ところが、学生隊長の命令って、ほとんどは学生隊長が出してるわけじゃないんだよね。



え?違うんですか?



世の中、そんなものはいくらでもあるよ。
例えば、未来が持ってる応用情報技術者試験の合格証書、経済産業大臣の署名が入ってるけど、あんなの経済産業大臣がいちいち作ってると思う?



言われてみれば……。あれ、名義貸しってことですか。



全く無責任に認めてるんじゃなくて、試験合格者に対して経済産業大臣の名の下に合格証書を発行して良いと、書面の作成や発行を委任しているから出来るんだ。



それと同じことが、この世の中ではよく行われている。
部下が必要な命令を考案して、権限を持った上司にお伺いを立てる。それを上司が承認することによって、命令が有効になるんだ。



権限を持った上司自身が自分で命令することって無いんですか?



無いわけじゃ無いよ。特に軽微な命令だと、指揮官自身が口頭でアレコレ命令をすることはよくある。
例えば、外出員点検がグダった結果、イラついた学生隊長が「点検やり直し!」と叫んだら……?これも命令と言えば、命令だね。



うへぇ……。そんな命令もあるんですか。



でも、学生服務要領とか、当直学生勤務要領とか、そういう複雑な文書は部下が作るのが普通。もし、いちいち学生隊長本人が作ってたらどうなると思う?



うーん、学生隊長がメチャクチャ忙しくなる……ですかね?



そのとおり。もっと言うと、本人の業務のキャパシティに全て左右されるようになってしまう。苦手な分野は進行が遅くなるし、指揮官自身が事実誤認していてもそれを指摘する人がいないまま、命令が成立してしまう。



だからこそ、細かい文章の作成は部下にやらせて、指揮官は部下の持ってきた案文が適切かどうかを確認するよう努めるんだ。



なるほど、さっき言ってた「組織的検討」って奴ですね。



そういうこと。これにはもう一つ利点があって、部下が「上位者の仕事」をするようになるんだ。
未来が学生隊長の……だと、ちょっと分かりづらいかも。ボクが艦長の命令を代わりに作って発する、それを繰り返すことで何が起きると思う?



うーん……。あ、艦長が何をしてるか、事前に勉強できるってことですか。



うん。ボクはあと何年かすれば副長に、10年ちょっとすれば艦長になる。そういうとき、副長や艦長が何をしてるか、ある程度分かった上で着任できれば、すぐに仕事に馴染むことができる。



なんなら、戦場に出れば、ボクより上の指揮官がみんな戦死して、ボクが一時的に艦長の仕事を代行しないといけないかもしれないんだ。だからこそ、普通の組織以上に、上の人はどんな仕事をしているのか知らないといけない。



なるほど、指揮官が全部自分で命令していると、指揮官が指揮不能になった時点で、何にも出来ない部下が残されて、戦えなくなってしまうんですね。
広告
文書は指揮官の承認を明確化



ここで、やっぱり命令は文書じゃないといけないって話になってくる。なんでだと思う?



伝言ゲームになるからですね。命令の内容を考えているのは部下なのに、それを承認するのは上司となると、きちんと文書にして上司に見てもらわないと、それこそ言った言わないの話になります。



そうでしょ?なんなら、上司にOKもらってない内容を、上司の命令だと騙って命令することすら可能になってしまう。まあ、文書でも同じことはできないワケじゃないんだけど、少なくとも後でバレる。
というわけで、指揮官が承認したことを明確化するためにも、文書で命令を出すことが重要なんだ。
広告



それはそれとして、私は何をすれば良かったんですかね?



学生隊長の命令を引っ張り出せば良かった……ということになるんだけど、さすがに「学生隊長命令」を候補生に作らせるワケがないんだよね。



何言ってるのか、意味不明だと思う。だから、次はこの「文書」という言葉が何を指しているのかを学ぼう。
この記事では、文書による命令等のプロセスについて、次の内容を説明します。
第1回
- 文書主義と組織運営
- 原則として文書による命令・報告に基づき、組織運営が行われる。
- 証拠性・同時性・客観性・保存性の利点のため。
- 組織を動かすには、組織的な検討を経て、適切な権限に基づく命令が必要
- 原則として文書による命令・報告に基づき、組織運営が行われる。
- 「上位者の仕事をする」ということ
- 指揮官が部下の提案を承認することで、命令が生まれる。
- 指揮官の命令を実際に作り発するのは部下
- 指揮官自身が能動的に命令を発すると
- 指揮官のキャパシティによる制約大
- 部下が育たず、指揮官が指揮不能になると組織が瓦解
- 指揮官が承認したことを明確にするために、文書が必要
- 指揮官が部下の提案を承認することで、命令が生まれる。
第2回
- 「文書」を巡る複雑な問題
- 海自での「文書」は状況により指すものが異なる。
- 「正式な文書」としての文書
- 「一般命令」や「通達類」など
- 経費の支出根拠になる。
- 艦長など官職印のある者(通常は1佐以上)だけが発簡できる。
- 発簡年月日と発簡番号が明記される。
- 「書面による情報伝達」としての文書
- いわゆる「報告資料」「実施要領」など
- 一定の体裁をもって、書面にまとめられている。
- 「正式な文書」のような効力は持たないが、情報伝達に用いられる。
- 「行政文書」としての文書
- 公文書管理法上の公文書
- 状況により、電子メール、写真、メモ書きなども含まれる。
- 保存や開示について法令を遵守する必要
- 「正式な文書」としての文書
- 文書について考える場合、どの「文書」を指すのかを明確に認識する必要
- 海自での「文書」は状況により指すものが異なる。


第3回
- 「行政文書管理の手引」を読み込もう。
- 「文書」の作り方
- 合議制
- 会議で意思決定する代わりに、関係者が順次案文に修正を加えることで調整
- Wordの設定
- 一般命令・通達類
- 起案用紙を用いるのが特徴
- 訓練実施要領
- 合議制
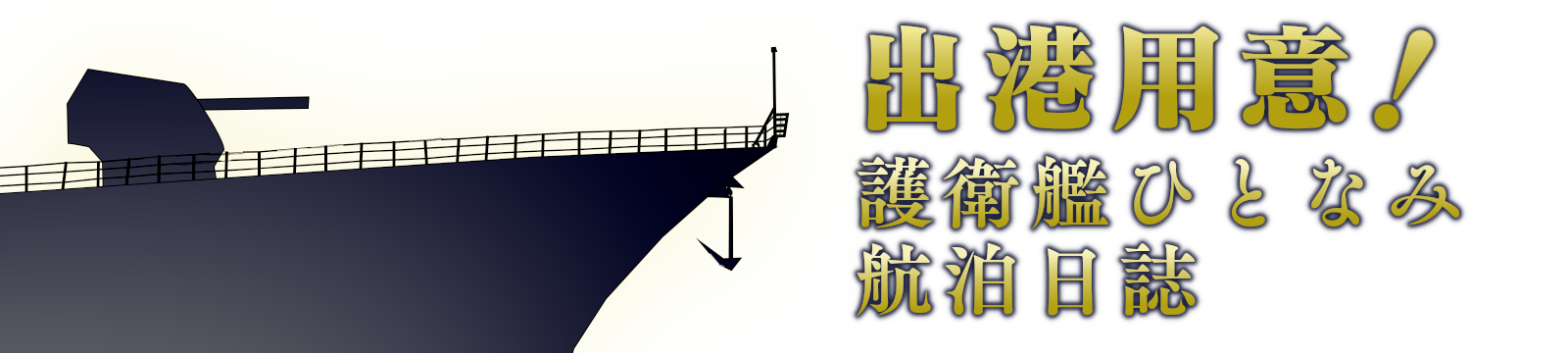
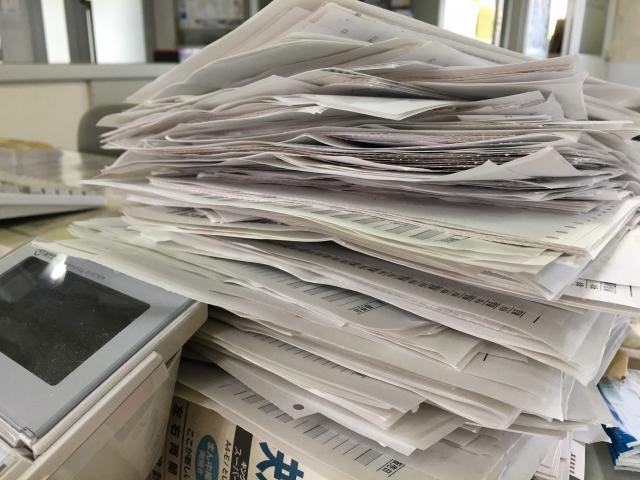






コメント