この記事では、自由で開かれたインド太平洋(FOIP)戦略について、次の内容を説明します。
第1回
- 概要
- 「自由で開かれたインド太平洋」は、太平洋とインド洋を、アジアとアフリカを繋ぐ国際公共財として捉え、自由なアクセスを維持することで地域全体の繁栄を目指す戦略・構想
- キーワード
- 法の支配、航行の自由、自由貿易等の普及・定着
- 沿岸国による不当な海洋アクセス制限を防止
- 経済的繁栄の追求
- 物理的・人的・制度的連結性を確保し、インド太平洋をより「使える海」に。
- 平和と安定の確保
- 沿岸国の法執行能力・防衛力強化に協力
- 海洋の治安を維持
- 法の支配、航行の自由、自由貿易等の普及・定着

第2回
- 背景
- 紛争の増大
- 東南アジア~アフリカは経済成長著しいが、海賊・テロ等の治安問題を抱え、政治的にも不安定
- 国家間紛争も根絶できていない状態
- アメリカの影響力低下
- 「テロとの戦い」に最適化してしまったアメリカ
- 国内での分断が進み、世界への関心を徐々に失うアメリカ
- 中国の台頭
- 爆発的な経済成長と軍事力整備
- 国際法と相容れない伝統的思想
- 独り勝ちを狙い、増えていく「辺疆」
- 紛争の増大
第3回
- 経緯
- 第1次安倍内閣における「自由と繁栄の弧」
- 価値観外交のはじまり
- 対中封じ込め策と認識されやすく、安全保障に十分踏み込めなかった。
- 第2次安倍内閣における「自由で開かれたインド太平洋」
- 防衛にも踏み込んだ、安全保障戦略として登場
- 軍事色を抑えるため、戦略は構想に
- アメリカの同調
- トランプ大統領が支持し、米国の国家戦略に採用
- 米太平洋軍がインド太平洋軍に改称
- 沿岸国・欧州の賛同
- 各国と安全保障に関する協定を締結
- 日本周辺への艦艇等の派遣が活発化
- 第1次安倍内閣における「自由と繁栄の弧」

第4回
- 意義
- 望ましい安全保障環境の創出
- 「力による一方的な現状変更」を否定する風潮が醸成されている
- 国際社会は日本の防衛力強化を容認
- アメリカ以外の「同志国」を獲得
- 対中封じ込め策ではない。
- 地域全体の繁栄を尊重すれば、中国も利益を得られる。
- 独り勝ちの断念を促す戦略
- 望ましい安全保障環境の創出
- 評価
- 「場」を創出する思想を明示した、戦後初「本物」の安全保障戦略
- アメリカを孤立と迷走から救い出した立役者
- 効果を得られるかは日本次第
- 新興国は、日本が本気か否か値踏みしている。
- 欧米諸国にも右傾化の兆し。国際協調への関心は徐々に損なわれつつある。
- 斜陽国家日本が世界を動かす。

 機関長 降旗3佐
機関長 降旗3佐それでは、FOIPが登場するに至った背景や経緯を説明するわね。



はい、よろしくお願いします。
背景



FOIPが登場した背景には、インド太平洋地域における紛争の増大や、米国の影響力低下、そして中国の台頭があるわ。
インド太平洋地域における紛争の増大



「紛争の増大」という話は、もっと正確に言うと「地域の経済成長が著しい一方で、沿岸各国の国内外での衝突が解消されていない」ということよ。



インド太平洋地域の特徴は、なんと言ってもその複雑さよ。
欧米は民族の違いはあっても、キリスト教や民主主義、市場経済といった一定の価値観でまとまることが出来たわ。対してアジアやアフリカは歴史的背景も言語も宗教も、何もかもが多様でまとまりが無いわ。



ですねぇ。国の中ですら公用語が通じないのがザラなんて場所もありますし。



欧米がまとまることが出来たのは、冷戦の影響も大きいわね。
共産主義陣営に立ち向かうためには、多少の対立は乗り越えて団結せざるを得なかったの。



アジア太平洋地域は東西世界から切り離された第三世界だったって話ですね。



この地域は戦後、特に冷戦が終結した後は、急速に経済成長を遂げたわ。先進国の経済成長が少子化に伴い鈍化していく中で、アジアやアフリカは人口増加も続き、順調に発展しているわ。



でも、価値観がまとまらず、法の支配などが適切に行われていないために、法的にも政治的にも不安定な状態が続いているわ。特に冷戦が終わる頃からは新興国の自律性が増してきたから、小競り合いが耐えなくなったわね。



そうなると……、法的・政治的に不安定な地域で、モノやカネが活発にやり取りされるようになるってことですか。



そういうことね。でも、物流がきちんと維持されるか分からない、支払いがきちんと行われるか分からない。そんなところと商売をするのは嫌でしょう?だから、新興国の法的・政治的な安定性を高めることが求められてきたの。



なるほど……。



とは言え、この要求はFOIPという概念が出来るよりずっと前からあったし、アメリカを中心として各地域の民主化、自由経済化を推進しようとする試み自体は前からあったわ。



その甲斐もあって、東南アジアは以前に比べてかなり安定してきたわ。けれど、アフリカは依然として安定しない国が多いわね。



そして問題は、この事情があった上で、アメリカの影響力が低下して、中国の影響力が増してきた事よ。
広告
アメリカの影響力低下



アメリカの影響力低下って、よく言いますけど。実際のところどうなんですか?今でも十分強いような気がするんです。



少なくとも冷戦期に比べれば遥かに弱くなったわね。
1961年のピッグス湾事件や1989年のパナマ侵攻など、良いか悪いかはさておいて、かつてのアメリカは意にそぐわない国の壊滅を企てるような、覇権とも呼ぶべき影響力を持っていたわ。
その影響力が最高に達したのが1990年の湾岸戦争だと言われているわ。



あー……。確かにそうですね。
「テロとの戦い」への最適化



それほどの影響力が何故低下してしまったのか。いくつか理由はあるけれど、そのきっかけの一つが2001年の同時多発テロ事件よ。



アメリカは同時多発テロへの対応としてアフガニスタンへ侵攻し、続いてイラク戦争を始め、20年以上にわたってイラクやアフガニスタンに軍を駐留させて、対テロ作戦を行わなければならなくなってしまったわ。



なるほど、軍の中での優先順位が変わってしまったんですか。



ええ。冷戦が終わって共産主義陣営との決戦に備える必要がなくなってしまったから、正規軍との大規模な戦争をするよりも、小規模なテロにどうやって勝つかを真剣に研究するようになったの。
つまり、「テロとの戦い」に最適化した結果、本来の軍隊が持つ機能を低下させてしまったのね。



米海軍と言えど、例外ではないわ。
2000年に発生したコール襲撃事件では、就役からわずか数年のイージス艦が自爆ボートによって大きな被害を受けたことから、民生用の小型飛行機や船舶による自爆攻撃への対応が求められるようになったわ。



そうでした。LCS(Littoral Combat Ship:沿海域戦闘艦)って、そこから始まったんでしたね。



ええ。沿岸域では自爆ボートのような安価な兵器による撃破の恐れが増すことから、高価で高性能な艦艇を展開させるべきではないという思想と、非軍事作戦の増大によって隻数を確保しなければならないという要求によって、安価で数を揃えられるLCSが生まれたの。



でも、そのLCSはミッションパッケージの実用化に失敗した挙げ句、沿岸域での作戦行動にも上手く使えなくて、調達が取りやめになったとか……。



ハードウェアに目が行きがちではあるけれど、中で働く人間への影響も無視できないわ。対テロ作戦や非軍事作戦が増えれば、当然、本来の正規軍との戦いを訓練することも減っていくわ。組織の雰囲気も徐々に変わっていくの。



確かに……。10年もすれば、新入隊員が中堅になりますもんね。
対テロ作戦しかやったことのない指揮官なんてのも現れます。



このあたりは映画を見ていても感じられるところではないかしら。
昔の軍事映画に出てくるベテランはベトナム戦争や湾岸戦争を戦い抜いた人として描かれていたけれど、最近の軍事映画だとアフガニスタン戦争やイラク戦争の英雄として描かれることが増えたわね。



そして、変わったのは軍隊だけではないわ。国民もよ。



あ……。そうでした。軍需産業の衰退ですね。



ええ。最近だと、ウクライナを支援しようにも、弾薬の生産が全く間に合わないという問題がよく報じられているわね。



アメリカという国自体が貧しくなったわけではないわ。でも、経済成長を続ける過程でムダを削ぎ落とし過ぎてしまったのね。



弾が無いのは日本だけだと思ってたのに……。



米海軍も同様よ。
軍艦の造修能力が低下の一途を辿っているわ。トランプ政権が355隻艦隊なんてプランを打ち出したけど、今や造船所は既存艦艇のメンテナンスと除籍艦の代替艦を建造するので精一杯。



ええと……?
空母を建造可能なのは1か所だけ、原潜を建造可能なのは2か所、イージス艦を建造可能なのも2か所……。



それだけではないわ。中国や韓国との価格競争に負けた結果、商船の造船能力も大きく低下させてしまったのよ。潜在的な建艦インフラが減るだけでなく、国内で造船業は斜陽産業としての地位を確立してしまって、技術者の質や量も減っていくわ。



あちゃー……。艦艇を増やそうとしても、簡単には造れない素地が出来てしまってますね……。
広告
深まる分断と孤立主義への傾倒



もう一つ、アメリカの影響力を低下させた原因は、世論よ。



アメリカはもともと格差の大きい国と言われていたけれど、リーマンショック以降は格差がさらに大きくなってきていると言われているわ。



格差の拡大は国民の分断を生むわ。
貧困層は当然ながら国内経済にしか興味がなくなっていくし、不満の矛先を求めるようにもなるわ。
トランプ政権が生まれた背景もまさにそれよ。アメリカは白人優位の国と思われがちだけれど、実際には工業の衰退によって貧困層へ没落した白人がたくさんいるの。そうした人々は、アファーマティブアクションによって優遇される黒人や、仕事を奪い合う中南米からの移民を排斥しようとするのね。



うーん。そんなことしても解決にはならないのに……。



ここで重要になるのは、そうした排外主義が国民の偽らざる本音である事よ。オバマ政権をはじめとする民主党政権は人種問題について寛容な姿勢を示したり、国内格差の縮小させるような政策を打ち出していたけれど、彼らが救いの手を差し伸べなかった弱者は少なくなかったということね。



こうして、政治の争点は国内へと急速へ移っていったわ。
「世界の警察」をやっている余裕はなくなるし、指導者層の関心も国内経済が支配的になっていく。



トランプ政権は中国に対して強硬的だったけれど、それも通商問題が主で、安全保障的観点での対中警戒はそれほどでもなかったと言われているわ。



そういえば、ウクライナ戦争の直前にバイデン大統領が不介入方針を示してましたね。





ええ。あそこでアメリカが強硬姿勢を見せなかったからこそ抑止が破綻してしまったという意見は根強いわ。
後になって失敗を取り返そうと、アメリカは急速に介入を強めたけれど、ここでこういう発言が出てきたこと自体、アメリカが世界への関心を失っていたことを物語っていると言えるわね。



「ひょっとしたらアメリカは何もしないかもしれない」
この疑念は、とても重大よ。



戦争を始めるハードルが下がりますもんね。



ええ。力による現状変更が抑止されているのは、事を起こせばアメリカが介入して大きな損害を被るであろう、という推定があるからよ。
その可能性が下がれば、力による現状変更が行われる可能性が高まるの。



そして、それは中国やロシアだけでなく、守られる日本の意思決定にも大きな影響を及ぼすわ。
「アメリカが動かないかもしれないなら、アメリカ任せは止めるべき」その危機感が日本を主体的な行動に駆り立てたのね。



うーん。確かに、「全部アメリカさんよろしく」って考えてた時代が健全かと言われると微妙ではあるんですが、果たしてこれはいいんだか、悪いんだか……。
広告
中国の台頭



アメリカの影響力低下と対になるのが、中国の影響力拡大よ。
爆発的な経済成長と軍事力整備



中国の影響力拡大は、何と言っても爆発的な経済成長によるところが大きいわ。
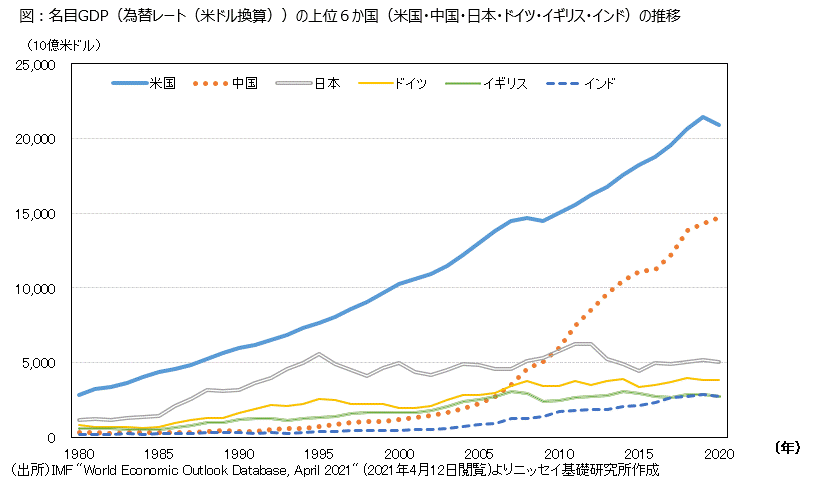
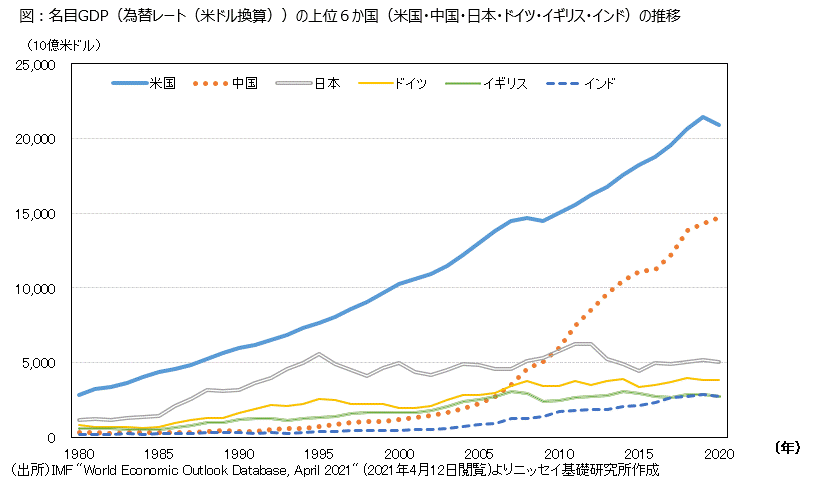



中国は世界トップクラスの人口と、中央集権体制による政治指導、そして部分的な市場経済導入によって、今や米国に迫る経済大国になったわ。



そして、その圧倒的な生産力を背景に、軍事力の増強も急速に進めているわね。



それは……本当にそう思います。肌で分かりますよ。
1年目と今では、出くわす中国艦の数も質も、全然違いますし。



中国は、2035年までに軍の現代化を基本的に実現し、今世紀中葉までに人民軍隊を「世界一流の軍隊」に築き上げるという目標を掲げているわ。



「世界一流」っていうのは、つまり「アメリカと同等の」って事ですよね……。



アメリカ対中国の軍事力を比較すると、国家全体の軍事力や、核戦力、空母運用能力では、まだまだ米国に分があると言えるけれど、東シナ海近辺に速やかに投射可能な戦力では、既に逆転が起きているわね。



そして、アメリカの軍事力整備の能力が既に衰退の一途を辿っていることは、さっき言ったとおり。当面は中国の軍事力増強スピードにアメリカが追いつくことはできないわ。



アメリカの力だけで中国を抑え込むことは、最早出来ないと……。
国際法と相容れない伝統的思想



そもそも、中国の影響力拡大が何故好ましくないのか。その答えは彼らの伝統的思想にあるわ。



伝統的思想、ですか?



端的に言えば彼らは真のところで、現代の国際法を受け入れていないの。



そういえば、国際法軽視ってこの前もおっしゃってましたね。



国際法上、主権国家はその力の大小に拘わらず、明確に線引きされた領土や領海を持つわ。



でも、彼らの考え方はそうではないの。
彼らにも領土や領海の概念はあるけれど、それとは別に「完全に国内ではなく、完全に国外ではない場所」があるの。
前時代の帝国によく似ている、と言っても良いわね。



……あっ、ひょっとしてそれって、辺疆ってやつのことですか?



あら、よく知っているわね。
そう、辺疆という言葉は「都から離れて寂れた場所」と解釈されがちだけれど、本来の使われ方はまさにそれ。決して自国そのものではないけれど、外国に面していて、自国の意によってコントロールできる。
その範囲は国境のように明確に線引きされるものではなく、国力によって柔軟に変動する面、グラデーションよ。



中国が領土問題でよく声明に用いる「歴史的に我が国の領土」というフレーズはそれを反映したものと言われているわ。かつての帝国の強い影響下に置かれた、つまり属国の統治していた場所は、中国にとって辺疆にあたるの。
だから、「中華人民共和国」という主権国家は一度として統治したことないけれど、歴史的には中国が統治する正当性があるから、現代の主権国家の考え方から言えば「領土」や「領海」とすることができる。



むちゃくちゃですね……。



漢や唐、明といった中国の帝国の影響下に置かれた地域と言うと、かなり巨大な範囲になって、東南アジアやインド洋方面まで飲み込むことになるわね。



……ん?ちょっと待ってください?
すると、日本はどうなるんですか?



日本だって、歴史的にはずっと朝貢貿易をしてきましたし、中国の文化的影響をかなり受けているじゃないですか。そうなると、ここは彼らにとっての辺疆になるんですか?



それは彼らにしか分からないわ。
でも、水雷長の言うとおり、日本の支配を正当化する彼らなりの論理が無いわけではないわね。もちろん、直ちに日本を占領してしまおうなんてことは考えていないと思うけれど。



一応言っておくと、この考え方自体は決して珍しいものではないのよ。
主権国家の考え方は、そもそも欧州人が勝手に取り決めたものが、のちに一般化したものよ。だから、アジアやアフリカの人々がそれを受け入れないことは不思議ではないわ。



でも、国際法は国際法です。今更そんなの嫌だなんて言っても……。



そうね。だから、法の支配を広めていく必要があるのよ。
広告
独り勝ちを狙い、増えていく「辺疆」



中国の拡大が好ましくない、もう一つの理由は、基本的に独り勝ちを狙っているからよ。



習近平政権は「一帯一路」を掲げて、インド太平洋地域での影響力拡大を図っているわ。
「一帯一路」は陸のシルクロード(一帯)と海のシルクロード(一路)を介して中国からヨーロッパまでを繋ごうという構想よ。そのために各国のインフラ整備などをサポートしようというわけね。



これ、前から思っていたんですけど、FOIPとやっていることはそんなに変わらないですよね。



ええ。法の支配や航行の自由などを推進する考え方を除けば、ね。



中国は爆発的な経済成長を背景に、港湾や道路などのインフラ整備の支援を急速に進めたわ。
日本やアメリカのような「西側」の国は、支援にあたって基本的人権の尊重や法整備について注文を付けることが多かったけれど、中国はそういう面倒な事を言わずに多額の融資をしてくれるから、多くの発展途上国が飛びついたの。



その結果、返済可能性を無視した多額の融資などによって、多くの国が債務不履行に陥っているわ。でも、その返済を免除する見返りとして、中国は港湾の使用権などを要求して、事実上の海外拠点、海外領土を着々と増やしているわ。いわゆる「債務の罠」というものよ。





まるでヤミ金ですね……。
というか、99年の租借権をって、中国が昔やられて酷い目にあったことそのままじゃないですか。



こうした海外拠点が、実際どのように使われているのかは明確にされていないわ。民生用なのか、軍用なのかも含めてね。



ただ、最近はカンボジアのリアム港のように、「一時的な寄港」だったはずの中国艦艇が、数ヶ月にわたって停泊を継続しているケースも確認されているわ。名目上は基地でなくとも、実際には中国の基地として利用されている可能性は否定できないわね。



つまり、これこそが辺疆であると。



そういうことね。影響力の及ぶ範囲、という意味で言えば、まさしく辺疆が拡大し続けていることになるわ。



そうやって、そもそも法的・政治的に不安定な地を、安定化させずに開発すればどうなるか。圧倒的な力を持つ中国だけが海洋へのアクセスを独占して莫大な利益を得ることができるのは明白よ。



なるほど、日本やヨーロッパの国が一帯一路に乗っからなかったのは、そういうことでしたか……。
広告



FOIPが登場した背景はだいたい分かったかしら?



ええ、ありがとうございます。



それでは、次はFOIPが登場するまで、そして登場した後、世界はどう動いたのか、その経緯について説明するわね。
この記事では、自由で開かれたインド太平洋(FOIP)戦略について、次の内容を説明します。
第1回
- 概要
- 「自由で開かれたインド太平洋」は、太平洋とインド洋を、アジアとアフリカを繋ぐ国際公共財として捉え、自由なアクセスを維持することで地域全体の繁栄を目指す戦略・構想
- キーワード
- 法の支配、航行の自由、自由貿易等の普及・定着
- 沿岸国による不当な海洋アクセス制限を防止
- 経済的繁栄の追求
- 物理的・人的・制度的連結性を確保し、インド太平洋をより「使える海」に。
- 平和と安定の確保
- 沿岸国の法執行能力・防衛力強化に協力
- 海洋の治安を維持
- 法の支配、航行の自由、自由貿易等の普及・定着


第2回
- 背景
- 紛争の増大
- 東南アジア~アフリカは経済成長著しいが、海賊・テロ等の治安問題を抱え、政治的にも不安定
- 国家間紛争も根絶できていない状態
- アメリカの影響力低下
- 「テロとの戦い」に最適化してしまったアメリカ
- 国内での分断が進み、世界への関心を徐々に失うアメリカ
- 中国の台頭
- 爆発的な経済成長と軍事力整備
- 国際法と相容れない伝統的思想
- 独り勝ちを狙い、増えていく「辺疆」
- 紛争の増大
第3回
- 経緯
- 第1次安倍内閣における「自由と繁栄の弧」
- 価値観外交のはじまり
- 対中封じ込め策と認識されやすく、安全保障に十分踏み込めなかった。
- 第2次安倍内閣における「自由で開かれたインド太平洋」
- 防衛にも踏み込んだ、安全保障戦略として登場
- 軍事色を抑えるため、戦略は構想に
- アメリカの同調
- トランプ大統領が支持し、米国の国家戦略に採用
- 米太平洋軍がインド太平洋軍に改称
- 沿岸国・欧州の賛同
- 各国と安全保障に関する協定を締結
- 日本周辺への艦艇等の派遣が活発化
- 第1次安倍内閣における「自由と繁栄の弧」


第4回
- 意義
- 望ましい安全保障環境の創出
- 「力による一方的な現状変更」を否定する風潮が醸成されている
- 国際社会は日本の防衛力強化を容認
- アメリカ以外の「同志国」を獲得
- 対中封じ込め策ではない。
- 地域全体の繁栄を尊重すれば、中国も利益を得られる。
- 独り勝ちの断念を促す戦略
- 望ましい安全保障環境の創出
- 評価
- 「場」を創出する思想を明示した、戦後初「本物」の安全保障戦略
- アメリカを孤立と迷走から救い出した立役者
- 効果を得られるかは日本次第
- 新興国は、日本が本気か否か値踏みしている。
- 欧米諸国にも右傾化の兆し。国際協調への関心は徐々に損なわれつつある。
- 斜陽国家日本が世界を動かす。


このページには防衛省をはじめとする、日本政府・官公庁のWebサイト、SNSアカウント等から転載されたコンテンツが含まれます。
転載にあたっては、「リンク、著作権等について(首相官邸)」「防衛省・自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」「海上自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」等に示される各省庁の利用規約を遵守しています。
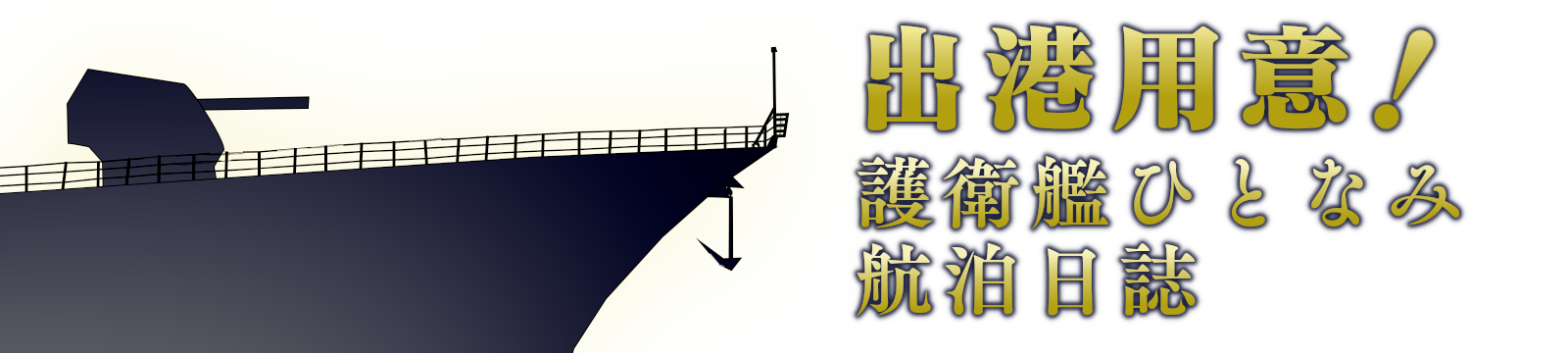





コメント