この記事では、護衛艦のパートについて次の内容を説明します。
- 「艦上救難」は、航空機の事故に際して消火作業や搭乗員の救出を行うパート
- ヘリコプターは非常に繊細な乗り物で、事故が発生しやすい。発着艦に失敗して飛行甲板上で墜落すれば、ヘリコプターだけでなく、艦の安全にも関わる大惨事となる。
- 艦上救難員は発着艦に際し事故に備えて消火設備などに配置され、火災が発生した場合は消火活動を行い、ヘリコプター内に取り残された搭乗員の救出を行う。
- 発着艦時に銀色の防火服を着ているのが艦上救難員。
- 飛行甲板付近には「TAS」と呼ばれる消火設備が設置されており、艦上救難員はTASを使用して消火を行う。
- TASは泡消火剤や粉末消火剤などを自在に使い分けることで、普通・油・電気火災全てに対応出来る。
- 機体が破損して搭乗員が脱出出来ない場合、機体を破壊して搭乗員を救出することもある。
- 状況に応じて火をコントロールする知恵と、爆発炎上するかもしれないヘリコプターに肉薄して救出を行う筋力・度胸を求められる、困難な仕事。
- 地上の飛行場で航空火災に対応する「地上救難員」が乗艦することで「艦上救難員」となる。
- DDでは機関科に3名配置され、応急工作員と同等の扱いを受ける。
- ワッチなども応急工作員と共同でこなすが、艦艇勤務に不慣れな地上救難員からは不評の模様。
- ヘリコプターを搭載しないDDGやDEには配置されておらず、飛行作業を行う場合は応急工作員が代行する。
- DDHでは飛行科に配置され、人数も多い。
- DDでは機関科に3名配置され、応急工作員と同等の扱いを受ける。
 応急長 出水2尉
応急長 出水2尉さて、機関科は次で最後です!



えっ……まだ何かあったっけ?



次に紹介するのは艦上救難員です。
銀色の防火服は艦上救難員の証



「艦上救難」は航空機の事故に際して消火作業や搭乗員の救出を行うパートです。



艦上って言うから何かと思ったら、ヘリコプターの話ですか。



ええ。ヘリコプターというのは非常にデリケートな乗り物で、固定翼に比べると事故が発生しやすいものです。燃料が満載されているヘリコプターが飛行甲板に墜落すれば、ヘリコプターだけでなく、艦だって無事では済みません。



なるほど、それでヘリコプターの火災を消す専門の人がいるんですか。
広告
TASを操り航空火災を消火
艦上救難員が補職されていない「あたご」型護衛艦が映されているため、実際には応急工作員と思われる。



艦上救難員は発着艦作業をする時、格納庫や飛行甲板に配置されます。
広報で銀色の防火服を着ている人を見たことがあるかもしれませんが、それが艦上救難員です。
格納庫や飛行甲板周辺には「TAS(Twin-Agent fire extinguishing System)」という特別な消火設備があって、艦上救難員は事故の発生に備えてTASを操作できる状態で待機します。



そのTASっていうのは、普通の消火設備とは違うんですか?



はい。艦内にある消火栓は海水をそのまま流すんですが、A火災(普通の可燃物)にこそ使えますが、B火災(油)やC火災(電気)には使えません。
その点、TASは泡消火剤と粉末消火剤を使い分けることができるので、A火災にもB火災にもC火災にも、オールマイティで対応出来るんです。



なるほど、燃料が燃えてたらB火災ですし、機内の発電機が動きっぱなしだとC火災になるかもしれないからですね。



あれ、そう言えば、前に先パイこのTASの話してませんでしたっけ?



えっ、何か言ったっけ……?
……あ、TASS(Towed Array Sonar System)のことか。
どっちも「タス」と読むけど、全く別物。ボクが前に言ったTASSは艦尾から曳航するパッシブソーナーのことだよ。
今応急長が言ってるのは消火設備のTASのことね。



そうだったんですか。ややこしいですね……。
広告
燃えさかる機体に肉薄……!



さて、TASが優秀な消火設備であるとは言え、ただ遠巻きに消火剤をまくだけが仕事ではありません。
ある程度火が収まってきたら、確実に火を消し止めるために機体へと近づいて消火作業を継続することになります。



おぉ……、それは怖い……。



このとき、ヘリの搭乗員が自力で脱出出来れば良いのですが、墜落するような状況では機体が変形して脱出出来ないことも十分あり得ます。
そんな時、艦上救難員はエンジンカッターなどの工具を用いて機体を破壊し、中から搭乗員を救出することもあります。



大切なことではありますが、機体がいつ爆発するか分からない中、突っ込んでいくんですね……。



ええ。
防火一般に言えることですが、火を消し止めるにあたっては、単に水や消火剤をまけばいいわけではなく、酸素の供給をいかに遮断するか、消火者の位置をいかに熱から防護するかを考えた上で、効率的な消火作業をしないと却って危険が増すこともあります。つまり、火をコントロールする知恵が必要なわけです。
それでいて、爆発するかもしれない機体にとりついて仲間を助け出す、筋力や度胸も重要になってきます。
決して簡単な仕事ではありませんね。
広告
何故「艦上」救難員?



そう言えば、どうして「艦上」救難員なんて名前なんですか?
艦のパート名なんだから、艦上なのは当たり前だと思うんですよ。
航空消火員とか、そういう名前にすればいいのに。



まったく、おっしゃるとおりです。ただ、これには理由がありまして。
「艦上救難員」なんて名前をしているんですが、彼らはそもそも艦艇乗りではないんです。



ん?……あ、ひょっとして、航空管制員と同じような感じですか。



ええ、特技職の名前は「地上救難員」、地上の飛行場で化学消防車の取り扱いなどを行う連中です。その地上救難員が経験を積んだ後で護衛艦に乗艦すると「艦上救難員」と呼ばれるようになるんです。



やっぱり、航空機のことはまず陸上で経験を積んでからってことなんでしょうか。



そうですね。人数も少ないので、消火や救出のやり方を十分に勉強させてから乗せています。



護衛艦にはどれくらい乗ってるんですか?



ウチみたいなDDだと3名くらい乗っているのが普通です。機関科で応急工作員とほぼ同じ扱いを受けます。
艦によって多少違いはありますが、ウチの艦ではワッチや艦内巡視も応急工作の一部としてやらせて、発着艦のときは反対に応急工作員も艦上救難員と同じ仕事をやらせています。



ふむふむ。



ただ、このやり方は地上救難員たちの間ではあまり好かれていないようです。艦艇乗組になる事自体が不慣れな仕事に転換することになる上、応急工作員の仕事は未知の仕事になりますから。



やっぱり、慣れない仕事というのは敬遠されるものですね。



ちなみに、ヘリコプターを搭載しない、DDGやDEには艦上救難というパート自体が存在しないよ。ほとんど飛行作業をすることがないからね。
飛行作業が必要になった場合は、応急工作員が代行するんだ。



DDHだとどうなるんですか?ヘリコプターをたくさん使うなら、また少し違うんでは?



うん。DDHの場合、航空管制員と同じく、飛行科に配置されるんだ。
人数も少し多くてだいたい10人くらい。
仕事のやり方も、格納庫と飛行甲板の位置関係なんかが全然違うし、飛行甲板上で小さな消防車を走らせたりするし、DDとは結構違うみたいね。



なるほど。ありがとうございました。
このページには防衛省をはじめとする、日本政府・官公庁のWebサイト、SNSアカウント等から転載されたコンテンツが含まれます。
転載にあたっては、「リンク、著作権等について(首相官邸)」「防衛省・自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」「海上自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」等に示される各省庁の利用規約を遵守しています。
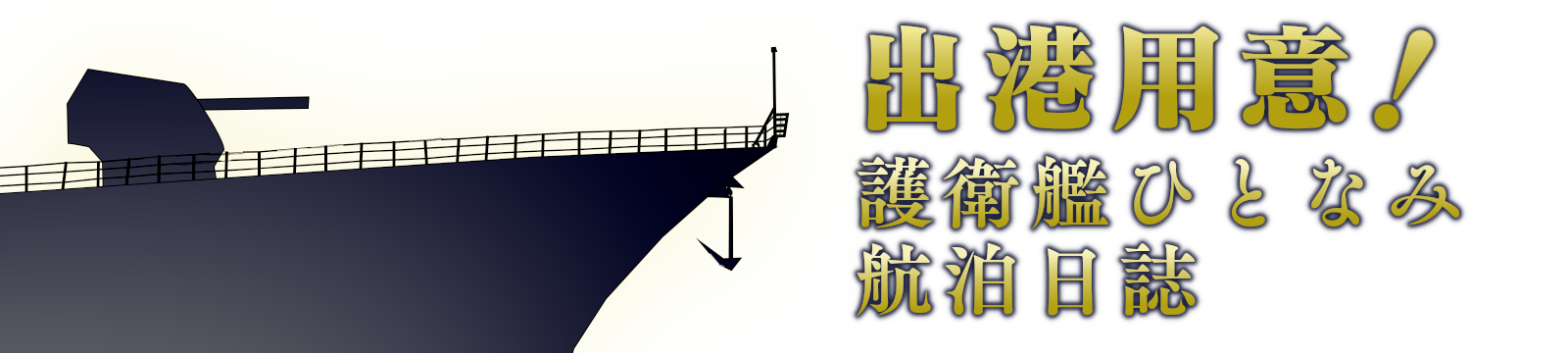




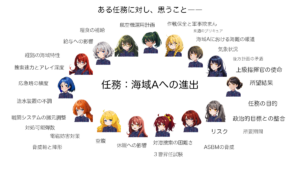

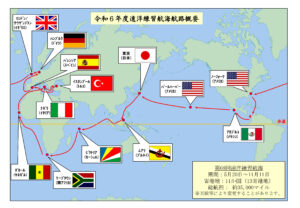


コメント