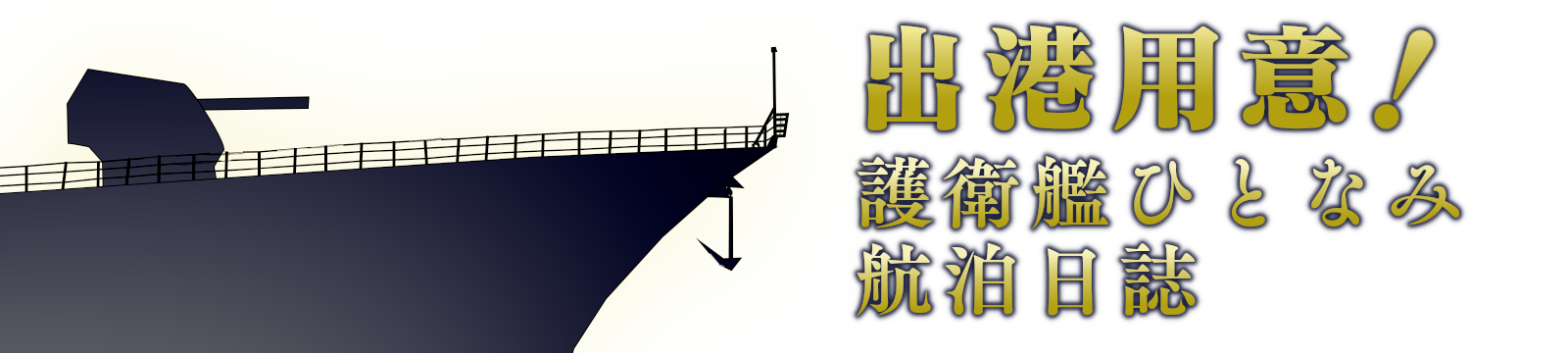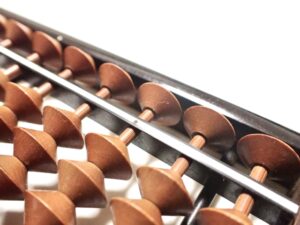目次
護衛艦とは何か
どんな護衛艦があるか
汎用護衛艦(DD)
「あさぎり」型護衛艦
ミサイル護衛艦(DDG)
準備中
ヘリコプター搭載護衛艦(DDH)
準備中
護衛艦(DE)
「あぶくま」型護衛艦
あわせて読みたい


この艦でよくここまでやる……!「あぶくま」型護衛艦 その1
護衛艦紹介シリーズ2隻目は「あぶくま」型護衛艦です。当初の運用構想とは異なる使われ方をしているため、悪い点が目立つのも否めません。
あわせて読みたい


この艦でよくここまでやる……!「あぶくま」型護衛艦 その2
「あぶくま」型護衛艦の紹介第2弾です。今回は、前回とうってかわって素晴らしい点を紹介していきます。
大きな艦には大きな艦の、小さな艦には小さな艦の良いところがあるのです。
護衛艦(FFM)
準備中
護衛艦にはどんな仕事があるか
士官室
準備中
先任海曹室
準備中
砲雷科
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:射撃員
今回から、護衛艦のパート紹介をしていきます。第1弾はやっぱり「射撃」。帝国海軍の時代から、「戦闘(先頭)分隊」といって、主砲の射撃員は編成表の一番最初に記載されていました。「護衛艦乗りになったからには、やっぱり自分で大砲を撃ってみたい」という方、是非射撃員に――、いやちょっと待って!この記事をよく読んでから、考えてみてください!
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:Phalanx員・SeaRAM員
近接防御火器(CIWS)、最近は機種名の「Phalanx」「SeaRAM」と呼ばれるようになりました。高度に自動化されており、いざ戦闘が始まれば特にやることは無い……なんてことはなく、自動化されているが故の苦労をたくさん抱えているパートでもあります。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:SSM員
今回は「SSM」。対艦ミサイル発射装置の操作・整備を行うパートです。
その特性から、装備が壊れることも少なく、業務負荷が軽いと思われがちですが……。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:運用員
今回は「運用」について解説します。名前を聞いても何をするのかよく分からないパートの代表格ですが、歴史は古く、人類が船を発明したときから「運用員」に相当する仕事はあった、と言われています。
今日はそんな奥深い、運用の世界をご紹介。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:水測員
今回は「水測」、すなわちソーナーです。ソーナー室に籠もって、一体何をやっているのか分からない人たち。そんな風に思っている人も少なくないはず。今日は、そんな水測員たちが何をしているのか、ご紹介。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:魚雷員・短SAM員・VLS員
今回は「魚雷」「短SAM」「VLS」について解説します。どうしてまとめるかと言えば、この3パートには密接な関係があるからです。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:CDS員
今回は「CDS」。指揮官が情勢判断したり、戦闘指揮したりするうえでなくてはならないCDSをメンテナンスするのが、CDS員の仕事です。
ところが、これを紹介するCDS長はなにやら複雑な心境のようで……!?
船務科・航海科
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:航海員
今回は「航海」です。航海長の頼れる右腕。伝統的に「信号員」と呼ばれますが、今どきの航海員の仕事は信号だけではありません。艦を目的地に安全に進めるためには彼らが必要です!
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:気象員
今回は「気象」です。たかが天気予報?と思うなかれ。天気を甘く見ていると艦が沈むことすらあるのです。
コンピュータによる気象予察が行われるようになった今も、気象員の意見は非常に尊重されます。その理由とは?
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:電測員
今回紹介するのは「電測」。「電波で測的するってことは……レーダーを操作する人だ!」と考えるのも無理はありません。ところが、電測員の仕事はレーダーの操作に留まりません。米海軍では「OS」と呼ばれる彼らの仕事はどのようなものなのでしょうか?
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:通信員
今回は「通信」の解説をします。
一言に通信と言っても、その言葉からみなが連想するものはバラバラ。インターネットを想像する人もいれば、無線電話を想像する人もいるでしょう。中には郵便を送ることだって通信だという人もいるかもしれません。今日はそんな漠然とした概念と戦う通信員を紹介します。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:電子整備員
今回は「電子整備」通称「ET」について解説します。船務科の中では目立たない彼らですが、レーダーをはじめとする様々な電子機器をメンテナンスして、ひとたび故障すれば全力で復旧に励む、心強い存在です。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:航空管制員
今回は「航空管制」です。護衛艦でヘリが発着艦する際、安全確認をせずにヘリを動かしていると、洋上とはいえ航空機同士の衝突など重大な事故につながりかねません。
航空管制員はそんな護衛艦の航空機運用を支える「洋上の航空管制官」です。
機関科
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:ガスタービン員・ディーゼル員
今回は「ガスタービン」「ディーゼル」です。艦に推進力を、電力を、水を、蒸気を、空気を届けるため奮闘する機械員の仕事について解説します。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:電機員
今回は「電機」について。あらゆるものが電気で動くこの時代、電力供給という生命線を握るのが電機員です。電球が球切れしたときや、電池が無くなったときにもお世話になりますが、当然ながらそれは電機員の仕事の枝葉の部分にすぎません。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:応急工作員
今回は「応急工作」について解説します。艦内の消防隊、あるいは町工場の職人、あるいは潜水のサポート役。様々な顔を持つ応急工作員の使命は「ダメージコントロール」。艦の任務遂行能力を維持する上で不可欠な存在です。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:艦上救難員
今回は「艦上救難」について解説します。ヘリコプターの発着艦に際して、火災が発生したときに化学消化剤を使って火を消し止め、ヘリに肉薄して中から搭乗員を救出するのが仕事です。人数も少なく目立たない存在ですが、頭も肉体も度胸も求められる、重要なポジションです。
補給科・衛生科
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:補給員
今回は「補給」を解説します。「補給」なんて名前をしているんだから、弾切れになったら弾薬庫から弾を持ってきてくれるのかな……?なんて思うかもしれませんが、やっぱり違います。補給員の実態は「倉庫番」。適正な物品管理に強い責任を持っている隊員です。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:給養員
今回は「給養」について解説します。昔から海上自衛隊、特に艦艇は食事の美味しさをセールスポイントにしてきました。その源泉となるのは腕の良い給養員たち。そんな彼らがどのような仕事をしているのか、解説します。
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:衛生員
今回は「衛生」です。医務室の主ですが、もちろん全ての医療行為が出来るわけではありません。とは言え、怪我人や急病人が出て一刻を争う時に、衛生員がどう対応するかでその人の行く末は大きく変わるのです。
飛行科
あわせて読みたい


護衛艦パート紹介シリーズ:飛行科員
護衛艦のパート紹介シリーズもとうとう最終回。最後を締めくくるのは「飛行科」。艦の能力を大きく左右するヘリコプターの運用に必要不可欠なポジションです。